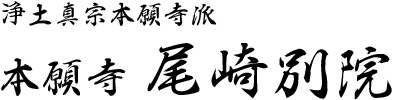お知らせ
-
2025.12.03
一気に冬の訪れ
-
2025.12.03
年末大掃除(御煤払)のお願い
-
2025.12.02
12月常例法座を開催しました
-
2025.12.01
令和7年12月法話 「即横超截五悪趣─そくおうちょうぜつごあくしゅ─」
-
2025.11.28
12月常例法座にお参りください
-
2025.11.28
報恩講法要3日目 満日中法要をお勤めさせていただきました
-
2025.11.27
報恩講法要2日目逮夜法要・初夜法要お勤めさせていただきました
-
2025.11.27
報恩講法要2日目日中法要をお勤めさせていただきました
-
2025.11.26
報恩講法要1日目をお勤めさせていただきました。
-
2025.11.26
報恩講2日目のお斎の準備が進められてます
カテゴリ